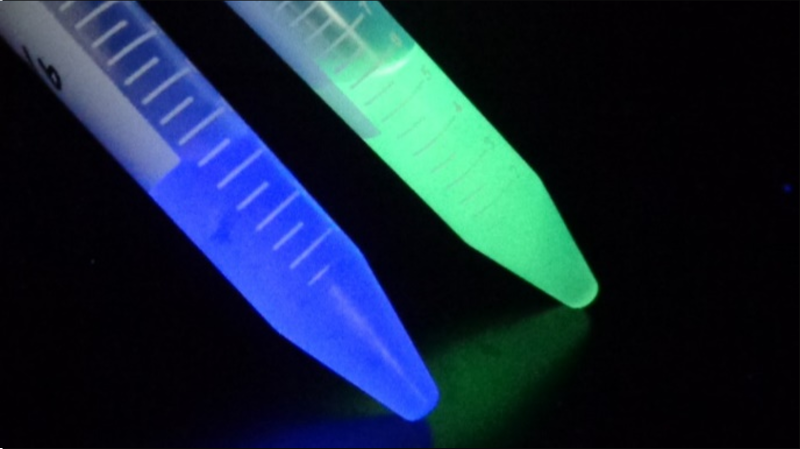Explore our technologies
Select categories
Topics
Application
field
Technical
Classification
List of technologies
List of applicable technologies
Unselected state shows recommended technologies
Co-Creation, R&D Base
We have places for dialogue and co-creation, and R&D bases that support our proprietary technologies, around the world.
News
2025-03-21
Konica Minolta and the University of Toronto Agree to Extend Joint Research Agreement for Five Years
2025-03-13
Konica Minolta’s Data Scientist Wins the Gold Medal in the World’s Largest Al Competition Hosted by Kaggle
2025-01-23
Konica Minolta to Launch the CM-SA2 Skin Analysis Software for Quantitatively Evaluating and Analyzing Skin Color as Well as Melanin and Hemoglobin